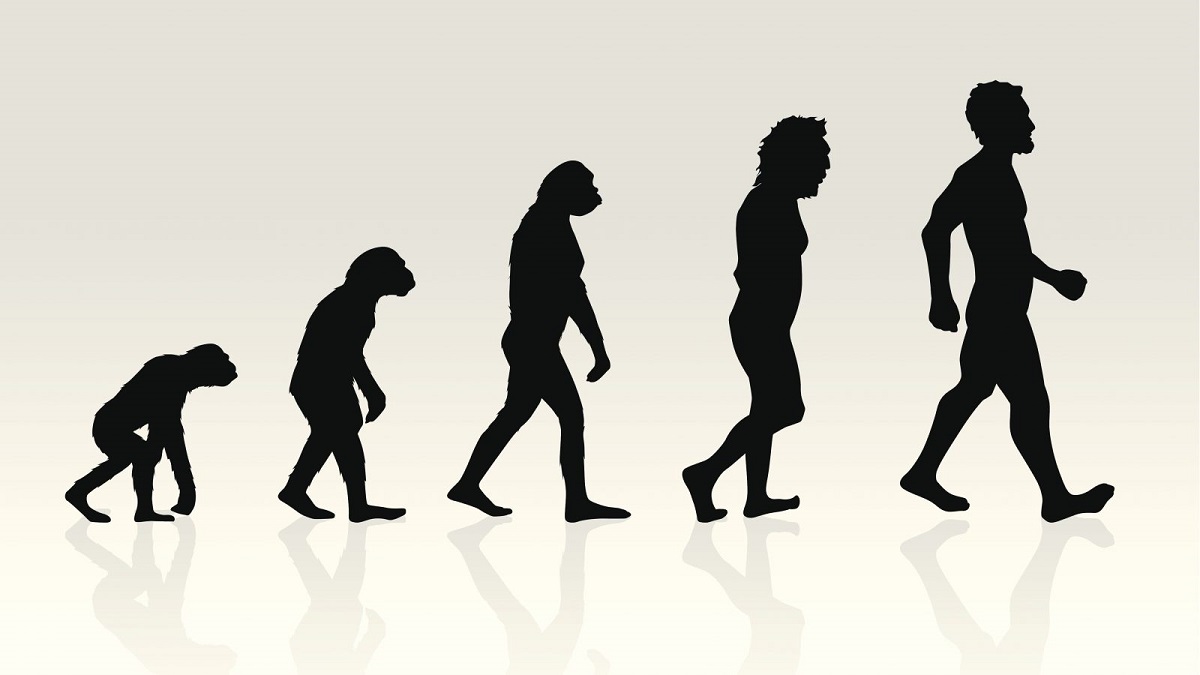
1万年後、人類の外見や性格はどう変化しているのか? 「進化の未来」を予測する
地球の生命は40億年の進化をたどってきました。
その進化が止まることはないし、人類の進化のペースはさらに加速する可能性もあります。
私たちの寿命、外見、脳のサイズ、性格、美の基準はこれからどんな変化を遂げていくのか、英バース大学の進化生物学者が予測します。
目次
私たちはまだ「完成形」ではない
人類が40億年にわたる進化で生まれたというのは信じられないような話です。
太古代(始生代)の海を漂っていた自己複製する分子が、カンブリア紀の深い海を泳ぐ目のない魚になり、さらに暗がりで恐竜から逃げるほ乳類へ、そして最終的に私たち人類が生まれたというのだから不思議です。
進化が人類をつくり上げたのです。
生物は不完全な形の繁殖をしてきました。
遺伝子の複製でエラーが生じると、それによってその生物の環境への適応度が高くなる場合があり、結果としてその遺伝子は次世代へ引き継がれやすくなったのです。
繁殖を重ねるとエラーも増えていきました。
このプロセスが数十億世代にわたって繰り返され、最終的にホモ・サピエンスが登場したというわけです。
しかし私たちはこのストーリーの最終地点ではなく、進化がここで終わることはありません。
そして人類の進化のペースはさらに加速する可能性があるのです。
たしかに未来の予測は難しいのですが、知識をもとに推測することはできます。
逆説的な言い方ですが、未来を予測するのに一番良い方法はおそらく、過去を振り返って、これまでの傾向が今後も続くと仮定することです。
そうすると人類の未来についていくつか驚くことがわかってくるのです。
アニメ脳で恐縮ですが、1万年後には巨大なスペースコロニーで人々が日常生活できるようになっていて、コロニー内の天気は計画的に雨を降らせたりもできるようになっていれば、さやっちのツイートのように多数決で天気が決まるかも!?(笑)
— よを (@yowo820) May 3, 2022
自然選択の終わり?
一部の科学者は、文明の台頭によって自然選択は終わりを迎えたと主張しています。
たしかに、捕食者や飢饉、伝染病、戦争といった、かつて強く働いていた選択圧はほぼ消滅しています。
飢饉や食糧不足は、高収量の作物と化学肥料、家族計画の普及によってほとんど起こらなくなりました。
暴力や戦争も以前ほど多くはありません。
私たちを捕食していたライオンやオオカミなどは絶滅したか、その危機に瀕しています。
そして数え切れないほどの人命を奪ってきた天然痘、ペスト、コレラなどの伝染病は、ワクチンや抗生物質、清潔な水が手に入るようになったことで制圧されているのです。
とはいえ進化が止まったわけではありません。
今では他の要因が進化の原動力になっている。進化というのは必ずしも「適者生存」ではなく、「適者繁殖」のプロセスだといえます。
人類は、自然の力で命を落とす可能性が低くなっても、パートナーを見つけて子供を育てる必要は依然としてあるのです。
そうなると、人類の進化では性選択が果たす役割のほうが大きくなります。
人類が作り出した文化やテクノロジー、都市などの人為的な環境は、新たな選択圧を生み出すが、これは氷河時代の人類が受けていた選択圧とはかなり異なる。人類はこうした現代世界に充分に適応できていないので、これから適応していく必要があります。
その適応プロセスは既に始まっています。
穀物や乳製品を食べるようになった私たちの遺伝子は、デンプンや乳糖を消化するように進化した。都市が過密化して病気が広がりやすい条件が生まれると、病気にかかりにくい遺伝子変異も広まりました。
そしてどういうわけか、私たちの脳は小さくなっている。人為的な環境では異常な選択が起こるのです。
こうした変化の行方を予測するには、前史時代を含めた過去600万年に起こった、さまざまな進化の傾向を調べることになります。
そうした傾向のなかで、農業と文明が発明された1万年前以降に出現した傾向は今後も続くはずです。
死亡率の低下なども新たな選択圧になっていて、この点では過去の傾向は参考になりませんが、他の種のケースを調べることはできます。
特に家畜の進化は人類との関連性が高いだろう。私たちは飼い慣らされたサルのようになってきているようですが、面白いことに、私たちを飼い慣らしているのは私たち自身なのです。
この先ではこうしたアプローチで、私たちの未来の寿命や体格、美の基準、知性などについていくつか予測をしていきましょう。
男女で争うことにより弱者男性は死に、女はほぼ全滅するが霊長類最強女子のみが生き残る世界線になって人類が進化するかもしれない。
— トリス(姫) (@oakandeggplant) May 4, 2022
寿命は何歳まで延びるのか
人類が長生きするように進化するのはほぼ間違いありません。
それもかなり長くなるでしょう。
ライフサイクルは死亡率、つまり捕食者や他の脅威によって命を落とす可能性に対応して進化します。
死亡率が高いと、動物は若いうちに繁殖しなければならず、そうしなければまったく子孫を残せない可能性があるのです。
またこの場合、老化やがんを防ぐ変異を進化させるメリットはありません。
そうした変異を使えるほど長生きしないからです。
死亡率が低いとこれが反対になります。
性成熟を迎えるまでに時間がかかるほうが良いのです。
また、寿命とともに繁殖可能期間も長くするように適応すれば、時間をかけて繁殖を行えるので好都合です。
孤島や深海に生息する動物など、捕食者がほとんどいない動物が長生きするよう進化してきたのはそのためです。
ニシオンデンザメやガラパゴスゾウガメは成熟時期が遅く、また数百年も生きることがあります。
人類の場合、文明誕生以前でも死亡率の低さと寿命の長さでは、類人猿と異なる存在でした。
矢と弓を持っていた狩猟採集民は捕食者から身を守ることができましたし、食べ物を分け合う習慣は飢えを防ぐことになりました。
そのため私たちは性成熟が遅くなるよう進化したし、長ければ70歳まで生きることもありました。
それでも子供の死亡率は高く、15歳以下の死亡率は50%を上回っていました。
平均寿命は35年しかなかったのです。
文明が誕生してからも、19世紀まで子供の死亡率は相変わらず高かったし、ペストや飢饉のせいで平均寿命は30年まで下がりました。
その後20世紀になると、栄養や医療衛生の向上によって子供の死亡率が低下。平均寿命は世界各国で70年まで急激に延び、先進国では80年になっています。
こうした延びは健康状態の改善が理由であって、進化によるものではありません。
しかしこの変遷は、進化による長寿命化の下地になるでしょう。
現在では、早くに繁殖を行う必要はほとんどありません。
それどころか、医師やCEO、大工などになるのに必要な訓練期間を考えれば、繁殖の時期は遅いほうが好都合なのです。
また、平均寿命は既に2倍になっているので、より長生きし、出産可能年数が長くなるよう適応したほうが有利になります。
100歳以上、あるいは110歳まで長生きする人が増えていることを考えると、私たちの遺伝子が進化して、平均的な人が100歳かそれ以上まで生きるのが日常になるという説には、充分な根拠があるといえます。
今0歳のある赤ん坊が何歳まで生きられるか、未来のことなので誰も確定的なことは言えない。だから、これまでに亡くなった人達の最後の年齢の統計を取って平均寿命を算出し、それをもって0歳児が平均的にはどれくらいの年数生きられるか目安を割り出す。これのどこが「言ったもん勝ち」なのか…… https://t.co/sI61pYmfKW
— 須賀原洋行 週刊アサヒ芸能で4コマ漫画『うああな人々』新連載。 (@tebasakitoriri) May 1, 2022
身長は縮むのか伸びるのか
動物の進化では、時間とともに体が大型化することが少なくありません。
ティラノサウルスやクジラ、ウマ、霊長類でそうした傾向がみられます。
ホミニン(ヒト科動物)も同じです。
初期のホミニン(アウストラロピテクス・アファレンシスやホモ・ハピリス)は背が低く、120~150cmほどでしたが、後の時代のホミニン(ホモ・エレクトスやネアンデルタール人、ホモ・サピエンス)では背が高くなりました。
その身長は歴史時代を通じても伸び続けており、それは栄養状態の改善に後押しされた部分もあるのですが、遺伝子も進化しているように思えます。
人類の身長が高くなった直接の理由ははっきりしませんが、死亡率が体格の進化を後押ししている可能性があります。
成長には時間がかかるので、寿命が延びれば成長する時間も長くなるのです。
しかしそれだけでなく、女性が背の高い男性を好むこともあるでしょう。
つまり死亡率の低下と性的嗜好の両方によって、今後も高身長化が進む可能性が高いということです。
現在では世界的にみてヨーロッパの人々の身長が高くなっています。
特にオランダ人が高く、平均身長は男性が183cm、女性が170cmです。
いつの日か世界中の大半の人がこのくらい、あるいはこれを上回る身長になるかもしれません。
背が高くなると同時に、体格はスリムになっています。
過去200万年の間に腕力よりも道具や武器に頼るようになって、骨格はよりきゃしゃになりました。
農耕によって定住化が進んだことで、座って過ごす時間が長くなったため、骨の密度が低下したのです。
現代社会では机やパソコンに向かったり、車を運転したりする時間が増えているので、こうした傾向は今後も続くでしょう。
あごと歯も小さくなりました。
初期のホミニンには、食物である繊維質の植物をすりつぶす大きな臼歯とあごがありました。
肉を食べ、火を使って調理する時代になると、あごと歯は小さくなっていきます。
そしてチキンナゲットやビッグマックみたいな加工食品があふれた現代の食生活ではさらに噛む回数が減ったため、あごは縮み続けているのです。
親知らず(智歯)はそのうち退化して消えることになるでしょう。
理想の美は…
人類は10万年前にアフリカを出た後、さまざまな部族に分かれ、砂漠や海、山、氷河などで遠く隔てられて暮らすようになりました。
世界のさまざまな場所で気候や生活様式、美の基準などの異なる選択圧が作用したため、人類は異なる外見を持つよう進化し、それぞれの部族が特有の肌や目の色、顔つきを持つようになったのです。
その後、文明の台頭と新しいテクノロジーの発明で、こうした集団が再びつながります。
侵略戦争や帝国の建設、植民地化、貿易によって集団は移動し、その先で交雑したのです。
現在では道路や鉄道、飛行機による行き来もあります。
私たちは自由に混ざり合って、世界中に広がる1つの集団になりつつあります。
その結果として生まれるのは、複数の人種ルーツを持つ人々からなる世界です。
明るい褐色の肌と黒い髪をした、アフリカ系とヨーロッパ系、オーストラリア系、アメリカ系、アジア系のルーツを持つ人の外見が世界の平均になっていくでしょう。









