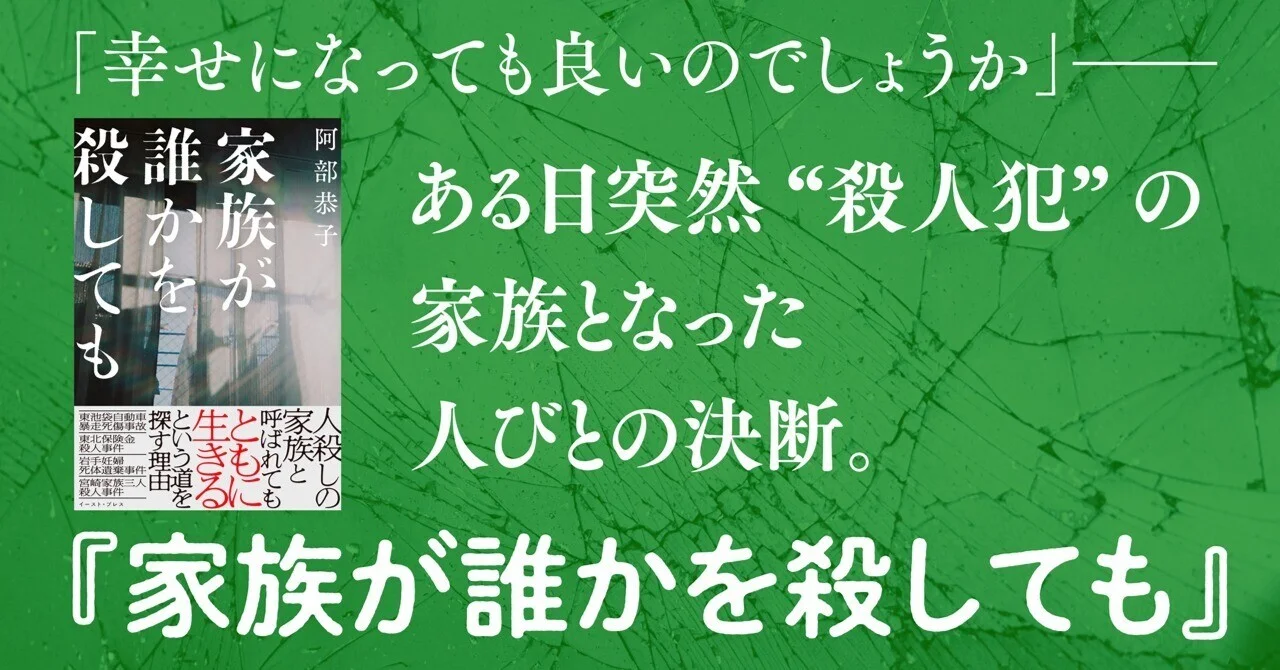
「池袋暴走」飯塚幸三受刑者、その家族が事故直後に体験した「猛烈なバッシング」の実態
2019年、元官僚である飯塚幸三(当時87歳)が自動車を暴走させ、11人を死傷させた「東池袋暴走事故」。
当時、飯塚受刑者の家族は、猛烈なバッシングを受けていました。
その実態を、NPO法人World Open Heart理事長として、加害者支援活動にたずさわってきた阿部恭子氏が明かします。
この記事は、阿部恭子『家族が誰かを殺しても』(イースト・プレス)の一部を、記事掲載に当たって再編集したものです。
目次
脅迫、中傷、嫌がらせの日々
妻と二人で暮らす自宅の住所は、事故直後にネットで拡散され、すぐさまさまざまな抗議や嫌がらせが手紙で届くようになった。
また、家の前で街宣車が抗議活動をしたり、記念写真を撮っていく人々まで現れた。
自宅の郵便受けには、「爆破予告」と書かれた紙が投げ込まれ、
「おまえの住んでいるマンションに小型爆弾を十個設置した。おまえが上級国民のまま逮捕されないまま呑気な顔で生活している天罰だ。この爆破でおまえを早々に地獄に突き落としてやる」
と書かれていた。
被害者の名前を使い、誹謗中傷する手紙を送りつけてくる人々もいた。
遺族感情に便乗したというより、事件をおもしろがってさえいるように思われるものばかりだった。
大学や専門学校の資料が大量に届けられる「送りつけ被害」もあった。
郵便を受け取るのはたいてい妻であり、心無い言葉の数々に心を痛めていた。
こうした脅迫や嫌がらせへの対応として、警察は転居を勧めたが、それでもまもなく90歳になる夫婦が容易に転居できるわけではなかった。
事件後、自宅に籠るようになった幸三の体力は、日に日に落ちていった。
事故直後の現場検証で、杖を突いて歩き回る幸三の映像が流れていたが、私の知る限りあの頃が自立して歩くことができる最後だった。
幸三の名前は全国に知れ渡っており、家を借りるに当たってもハードルは高くなる。
裁判が終わるまでは、どこへ逃げようともマスコミは追いかけるであろう。
新居が明かされれば今度は「図々しく逃げた」と批判される。
我慢して留まるしか、選択肢はなかったのである。
幸いにも、近隣住民は夫妻に同情的で、出て行けなどと言う人はいなかった。
周辺取材をした記者たちも「庶民的な夫婦で、近所の評判はいい」と証言している。
家族の雰囲気からも、幸三は世間で言われているような人物ではないと思われた。
取材依頼や自宅への嫌がらせに対して、弁護人が対応することはなかった。
一部の記者から「会見を開くべき」という声もあり、私は悩んでいた。
今更何を言ったとしても、火に油を注ぐだけに思えたのだ。
それでも、明らかに間違った事実が世の中に拡散された状態で、裁判に突入してよいのかという思いもあった。
加害者は沈黙するしかないのだろうか……、前例のない事態に、私は思い悩んでいた。
本日(11月17日)発売予定のこちらの単行本、welle designで装幀を担当いたしました。
『家族が誰かを殺しても』阿部恭子(イースト・プレス)
重大事件の加害者家族に寄り添う著者が描く加害者家族の現実とその後の人生、現代日本の「家族」のいびつな形とは。ぜひお手に取ってみてください。(Y) pic.twitter.com/QYyr5hcPL7
— welle design (@welle_design) November 17, 2022
誤報訂正記事の大炎上
私はこの頃から、ウェブメディアで事件に関する記事を寄稿するようになっていた。
一般メディアにとってはアクセスが難しい加害者家族の実情を、直接発信することができるからである。
もし家族の真実を報道してもらうならば、家族に報道陣の前で話してもらう必要が出てくる。
幸三の家族は、報道陣に囲まれるのに耐えられる精神状態ではなかった。
しかし、この一方的な報道の流れはどこかで変えていかなければならないと思った。
考えた末、講談社のサイト「現代ビジネス」で、「『上級国民』大批判のウラで 池袋暴走事故の『加害者家族』に起きていたこと」という記事を初公判の日に公開することになった。
2020年10月8日、東京地裁で開かれた初公判。
被告人・幸三は罪状認否で、遺族と被害者への謝意を述べた後、
「起訴状の内容については、アクセルペダルを踏み続けたことはないと記憶しており、暴走したのは車に何らかの異常が生じたため暴走したと思っております。ただ暴走を止められなかったことは悔やまれ、大変申し訳なく思っております」
と主張し、過失を否定した。
この発言に、世間では「不逮捕バッシング」に続く「無罪主張バッシング」が起こり、私が寄稿した記事も瞬く間に大炎上する騒ぎになってしまった。
加害者家族の苦しみに共感を示したコメントには非難が集中し、次々と炎上していた。
「大丈夫ですか……」
この異常事態を、長男はもっとも心配していた。
私はコメントをいちいち確認してはいなかったが、長男はその後の影響を気にかけていたのだ。
ネットでは、ネガティブな発言や過激な批判が目立ち、加害者側に少しでも寄った発言には火がつきやすく、中立的な意見は可視化されにくくなる。
しかし実際は、「やはりマスコミはひどい」といった偏向報道を批判する声や、
「家族と加害者は切り離すべき」といった趣旨に賛同する意見が、当団体にも電話やメールで多数寄せられていた。
しかしながら、
「飯塚を庇うならおまえも地獄に道連れにしてやる!」
「殺すぞ!」
といった脅迫もあった。
私はこれまでも数々の重大事件の加害者家族を支援してきたが、これほどまでに矢面に立たされた経験はなかった。
しかし、本気で加害者家族を支えていくならば、その役割は避けられないと決断した。
支援に「報道対応」と掲げてきたものの、一時的に家族が身を隠す手伝いしかできず、対策としてあまりに不十分で中途半端だという思いもあった。
報道された事実はすべて記録として残る。
過去はすべて黒い噂で塗りつぶされ、歴史になってしまう。
そしてその歴史は、犯罪者の子孫たちの社会的評価にまで、影響を与えているのである。
沈黙することが加害者側として正しい姿勢なのか。
さらなるバッシングを引き起こすリスクを取っても、事実は事実として伝えていかなければならないのではないかと考えたのだ。
当然、決断は家族の意志による。
悩んだ末、前例がない中報道に踏み切るに至った。
誹謗中傷に関しての刑事裁判でした。
・松永氏を侮辱する意図はなかった。
・松永氏に対してではなく、違う事故の遺族に言った。
・真菜と莉子の名前は誤入力でたまたまそうなった。という主張でした。
何を主張するのも彼の権利ですが、この内容でその主張はあまりにも無理があるなと思います。 pic.twitter.com/31du8dzAzp— 池袋暴走事故遺族 松永拓也 (@ma_nariko) November 16, 2022
孤立無援の上級国民
私は仕事で傍聴が難しい長男に代わって毎回、刑事裁判を傍聴することになった。
家族の席は被告人席の目の前と決まっており、すぐ後ろは記者席である。
傍聴人は、職員の指示通り順番に入廷するのだが、私が入廷を許されるのはたいてい最後で、周囲から、関係者であることは一目瞭然だった。
幸三を乗せたタクシーが裁判所に入るところでは、毎回、報道陣が詰めかけ車内の様子を撮影していた。
その傍らで、大声で罵声を浴びせかける人もいた。
毎回、一般傍聴券を求める人々も多数詰めかけており、閉廷して裁判所を出るまで何が起こるかわからない不安に包まれ、緊張が解けなかった。
また、開廷からしばらくは、どこから怒号が飛んでくるかと、審理に集中することができず、内容が頭に入って来なかった。
弁護側は、事故原因として車の故障を主張しており、前半は、車の故障に関する専門的な議論が続いていた。
しかし司法記者たちが車の故障について詳細に報じる裁判記事はほとんどなく、注目が集まったのは被告人の法廷での態度であった。
車椅子に深く腰かけ、机を見ている幸三を「眠っていた」「下ばかり向いてやる気がない」と批判したのである。
幸三は時々、目をつむる瞬間があり、遠くの席からは眠っているように見えたかもしれないが、私は毎回、その姿を目の前で見ており、居眠りするようなことはなかった。
私が見た被告人の中には、足を広げて踏ん反り返るような姿勢で座っていたり、挑発的、反抗的な言葉で応答する人々もいた。
開き直った横柄な態度は非難に値するだろうが、「無表情」「下ばかり向いて」と言われても、一体、どのような表情で、どこを見ればよいのだろうか。
毎回、ハンカチで涙を拭いながら検察側の主張に頷くような姿が「理想的な加害者像」なのか。
私は首をかしげてしまった。
本件の刑事裁判は、審理の内容よりも、被告人の一挙手一投足にのみ関心が集まり、批判の材料とされていた。
被告人は無罪を主張していたことから、更生について家族が情状証人として証言する機会はない。
家族は裁判を見守るのみであり、私は弁護人とはかかわりがなかった。
無罪主張はあくまで被告人の主張であって、家族の助言の下に進めているわけではなかった。
不逮捕も長男の仕業だと囁かれ、裁判に関してまで関与を疑われては適わない。
それゆえ、私はあえて家族の支援のみにとどまり、被告人の幸三とは距離を置くことにしていた。
刑事裁判ではじめて幸三の様子を見て、私もまた「上級国民」という世間の印象が刷り込まれていたことに気が付かされた。
これだけ日本中を騒がせた事件にもかかわらず、弁護人は二人。
報道対応にしても、裁判への対応にしても、あまりにも脆弱だった。
元通商産業省の官僚の肩書から、世間はあたかも幸三を、黒いものでも白くできる力があるかのように仕立て上げていたが、実際に目の前にいる幸三の姿はあまりに無防備な「普通の人」で、衰えた身体は小さく弱々しかった。
そもそも、権力を自由に行使できるならば、我々のようなNPO団体などに家族が支援を求めるはずがない。
私は本件を機に、改めて理念としてきた「社会的弱者の救済」について、再定義を余儀なくされていた。
社会的弱者といえば、貧しい人やさまざまなハンディキャップを持つ人々を想像するだろう。
そのような定義に幸三や家族は当てはまらない。
しかし、世間の憎悪の対象となり反論ができない立場に追い込まれている彼らは、社会的に追いつめられており、そういう意味では、弱者であるとも捉えることができる。
幸三ほどの経歴の持ち主は稀かもしれないが、これまで、医師や弁護士といった高度専門職の加害者家族や、元官僚、東大卒といった高学歴の加害者の家族も支援してきた。
彼らは幸三同様、犯罪とは無縁な人生を歩んできたゆえに、事件後は無防備で、報道陣や捜査機関への対応に苦慮していた。
加害者の社会的地位が高ければ高いほど、社会的責任は厳しく問われることになる。
世間には、「持てる者」たちの転落を面白がる人々がいるのも確かだ。
このような状況に陥った加害者家族を支えるには、暴走する世間の行き過ぎた制裁に歯止めをかけるべく、発言していかなければならない。
その過程で支援者である私も、世間の憎悪と対峙することは避けられなかった。
メディア全体の批判に繋がって欲しくはないので、一言だけ書きます。
今まで、沢山の現場の記者の方々が、中立を保ちつつ、「交通事故を無くしたい」という私の想いを熱心に取材してくださいました。
私の発言によって、「メディア全てがおかしい」という印象になって欲しくはないので書きました。
— 池袋暴走事故遺族 松永拓也 (@ma_nariko) November 14, 2022
ネットの声
「この事故が誰によって起こされたか。そしてそれに真摯に向き合ったか。ブレーキなど製造者に責任転嫁するなどが当事者の行動のほとんどだったと記憶している。
その間のご家族へのバッシングは確かに看過できるものではないが、起きた事実に当事者もそのご家族も向き合わなかったのではないだろうか?それを世間から感じられないようになって今まで過ごしてきた人間がいた。というのも今回の事故の教訓にしなければならないと思います。
今の時代、私自身も、場合によっては自己否定を含めて真摯に世の中に向き合うことこそ重要だと思うようになりました。」「飯塚の態度は開き直っているようにも感じ取れたからな…。
それが呆けてたとしても罪の意識も感じ取れなかった。
自動車に問題があってブレーキを踏んでいたという意見を変えることもなかったし叩かれるには条件が揃っていた。
先日、移動中に新宿で被害者支援センターのイベントが開催されてたから寄ってみたけど、展示内容や配布されている小冊子に綴られていた被害者遺族の思いは本当に苦しくなった。
今回の件は加害者家族に法的に罪はなくても心情的に罪はないともいえない。高齢者なのに(半ば強引にでも)返納させなかったこと、運転させたことなど加害者家族にも責められる理由はあった。」「しかしまたそれもまた偏った意見なのだよ。とても中立的とは言えず、解釈に美化が伴う。
家族に責任はないかもしれないが犯罪被害者が思考から除外されている。
真に中立の立場なら双方の真実を考慮すべきだよ。被害者の救済があってから加害者の救済があるべきなのだ。事が起こればそれに伴う因果が生じる。事が起こらなければ本来は何も無かったのだから。」
家族が誰かを殺しても 阿部恭子 (著) イースト・プレス (2022/11/17) 1,870円
「幸せになっても良いのでしょうか」
――人殺しの家族と呼ばれても、ともに生きるという道を探す理由。
ある日突然、家族が殺人を犯してしまった。
加害者家族と呼ばれる受刑者の家族は、その瞬間から、
過剰なマスコミ取材、ネット上での根拠のない誹謗中傷やいやがらせを受け、
辞職に追い込まれる、引っ越しを余儀なくされるなど悲惨な生活を強いられる。
そのような状況でも、罪を犯した家族を支え、そして更生の道を探るべく「ともに生きる」決断をするのは、なぜか。
重大事件の加害者家族に寄り添い続ける著者だからこそ描けた加害者家族の現実とその後の人生、
そして現代日本の抱える「家族」のいびつな形とは。
【目次】
はじめに
第一章 上級国民と呼ばれた家族――東池袋自動車暴走死傷事故
第二章 夫の無実を信じる純粋な妻の悲劇――東北保険金殺人事件
第三章 揺るがない兄弟の絆――岩手妊婦死体遺棄事件
第四章 死刑囚の母として――宮崎家族三人殺人事件
第五章 なぜ加害者家族支援を続けるか
第六章 家族はどこに向かうのか
参考文献
著者について
阿部恭子(あべ・きょうこ)
NPO法人World Open Heart理事長。2008年大学院在学中、日本で初めて犯罪加害者家族を対象とした支援組織を設立。全国の加害者家族からの相談に対応しながら講演や執筆活動を展開。今まで支援してきた加害者家族は2,000件以上に及ぶ。2021
著書に『家族間殺人』『家族という呪い:加害者と暮らし続けるということ』『息子が人を殺しました:加害者家族の真実』(すべて幻冬舎)『加害者家族を支援する:支援の網の目からこぼれる人々』(岩波書店)など。
|
|











