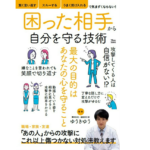『悪人』『怒り』を超える愛の衝撃!
吉田修一史上「最悪の罪」と対峙せよ。
琵琶湖近くの介護療養施設で、百歳の男が殺された。
捜査で出会った男と女―謎が広がり深まる中、刑事と容疑者だった二人は、離れられなくなっていく。
一方、事件を取材する記者は、死亡した男の過去に興味を抱き旧満州を訪ねるが。
昭和から令和へ、日本人が心の底に堆積させた「原罪」を炙りだす、慟哭の長編ミステリ。

「2019/10月に読んだ「逃亡小説集」以来の吉田修一。堅気になり切れない自滅する「逃亡者」たちを描いた良き短編集でした。しかしながら、今回は「悪人」に始まり、「さよなら渓谷」、「怒り」へと連なる犯罪小説と向き合うことになりそうですので、少し構えながら(暗い気持ちになるのを恐れながら(笑))「湖の女たち」(吉田修一 新潮社)を一気に読み終えました。
琵琶湖近くの介護療養施設「もみじ園」で、百歳の男が低酸素脳症により亡くなります。彼は果たして人工呼吸器の不具合によって、それとも当直の看護師、介護士たちの業務上過失により亡くなったのか?あるいは殺害されたのか?捜査する「西湖署」の刑事たち。就中、等身大の刑事・濱中。「もみじ園」で働く介護士・佳代。そして、その事件を取材することになった雑誌記者・服部の視点から、主にその事件がパラレルに語られていきます。作者が描き続けてきた今までの犯罪小説よりもそのミステリ的興趣が増幅されているように思えますので、今回もまたストーリーを細々と書くことができませんが、この犯罪を通して「この国」の”罪”を描き尽くそうとして選択されたマテリアルとアクチュアルな視点はより鋭利に研ぎ澄まされています。
湖岸の地方都市、介護養護施設、白い軽自動車、YouTubeの映像、どこにでもいそうな男と女。前であったとしてもその閉塞感は充満し、幸せの感じられないリアリティに打ちのめされ、何も変わらない、変えようとしない日本という国にひと匙ほどの<希望>も見いだせない日々を送る(私を含む)名もなき人々。
旧琵琶湖ホテルの特別展示室に飾られていた一枚の写真が死亡した男の過去を引き寄せ、旧満州のある湖の湖岸へと事件はフラッシュ・バックしていきます。中盤と終盤とでそれぞれ二つの湖を描写する作者の筆致、文章のリズム、メタファーを削ぎ落したその言葉の集合体は限りなく美しく、そのカッティングは映像魔術のようだと思います。
そして、ここで描かれている「恋愛」のようなものは、虚構のようでいて、実は我々の周辺に散らばっていて、誰もが体験していながら表立って語ることができない男と女の或る在り様をシンボライズしているように思えます。作者は(いつものことではありますが)見る勇気が持てないでいる傍らにある絶望的な<リアリティ>を今回は「架空の生き物」をそこに代入することによって救済しています。
ミステリ的興趣については具体的に書くことができませんが、間違いなく背筋を震わす瞬間があります。読後、少しの間目をつぶると、かの地を飛び立った丹頂鶴の群れが琵琶湖に降り立ち、積雪のように真っ白な<イノセンス>を告発するイメージにきっと満たされることでしょう。
<母性>を拒否した、あるいは手離した男たちだけが「湖の女たち」を真から救済することができるのかもしれません。見事な幕切れだと思います。」
|
|