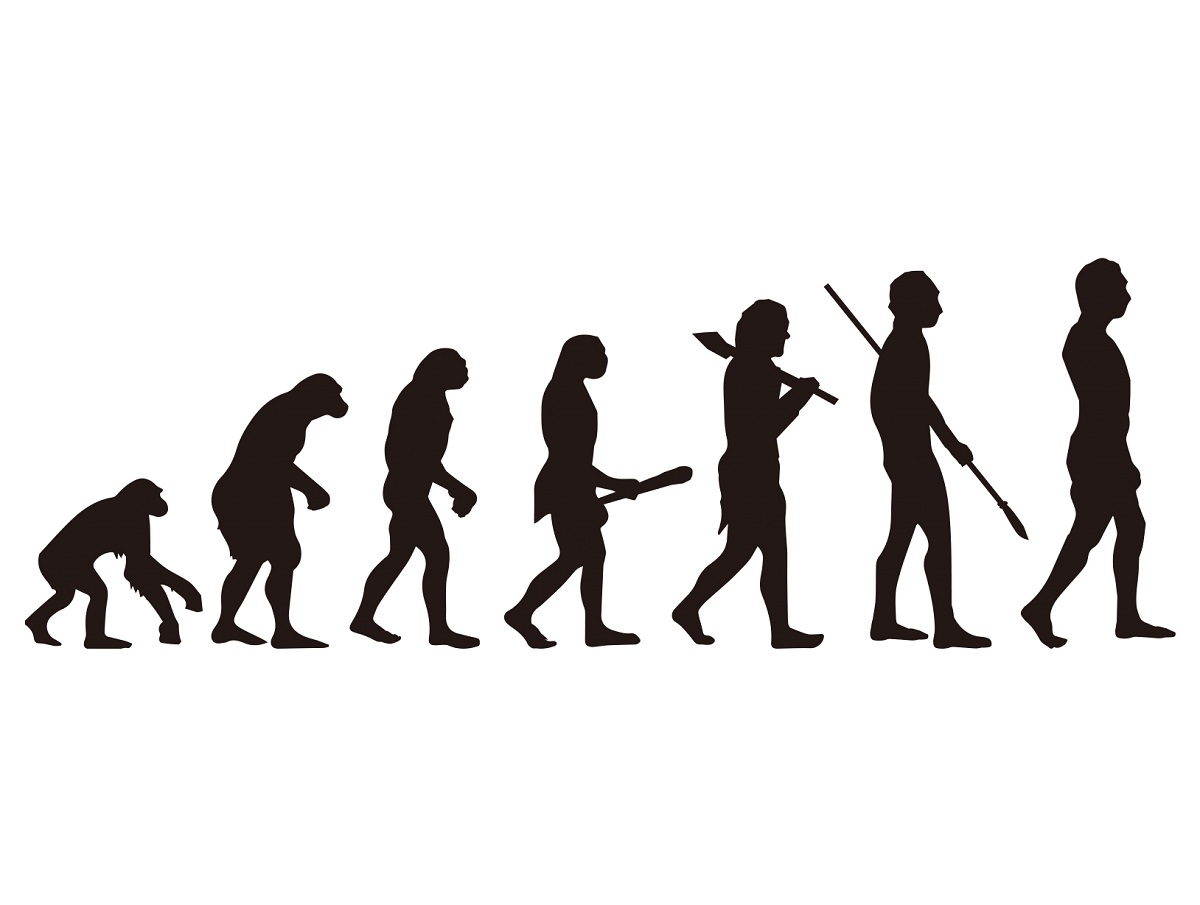
実はこうじゃなかった?! 「人類進化の行進図」を描き変える「新説」とは?
人類の直立二足歩行は、ゴリラやチンパンジーなど類人猿との決定的な違いとされ、人類進化の象徴のように思われています。
しかし、どうも違うらしいのです。
いや、人類の祖先が類人猿から分かれてから、直立二足歩行を始めたという「定説」自体が間違っているのではないかというのが、ジェレミー・デシルヴァさんの書いた『直立二足歩行の人類史』(文藝春秋)の主張です。
目次
「人類進化の行進図」は間違っていた?
人類の歴史について書かれた書物には、「人類進化の行進図」といったものがよくありますが、それは手を付いて歩く「ナックルウオーク」姿の類人猿から徐々に手を地面から離し、腰をかがめた姿勢から直立二足歩行になっていく、教科書でもおなじみのあの図です。
それは、類人猿の系統樹で、人類の祖先がチンパンジーなどから分かれ、その系統樹の先に直立二足歩行が進んだという認識とともに、我々の頭に刷り込まれています。
しかし、本書によれば、人類がチンパンジーなどと枝分かれするずっと前の共通の祖先の類人猿は直立二足歩行をしていたらしいのです。
それがドイツで発見された今から1100万年前に生きていた「ダヌビウス」の化石からわかるというのです。
『直立二足歩行の人類史』#読了
古人類学の研究成果からは人類が二足歩行する理由を探り、現代人の生態からは歩くことの重要さを説く。教科書などにも掲載されている、「人類進化の行進図」が誤りだと示唆する仮説はインパクトが強い。現代人にとっても歩くメリットと、歩かないデメリットが明白に。 pic.twitter.com/MxHueIfFaG
— ikawa.arise (@ikawa_arise) August 24, 2022
恐竜も鳥も二足歩行していた
「足首」を専門とする古人類学者で、米ダートマス大学人類学部准教授のデシルヴァさんは、初の著書となる本書で二足歩行を特別視していません。
地球上には、類人猿以外に「二足歩行」する動物はいましたし、今も存在します。
古くは白亜紀の恐竜ティラノサウルス・レックスは二足歩行で獲物を捕らえていましたし、ほかにも多くの二足歩行の恐竜はいました。
そういえば、ティラノサウルスはゴジラのモデルとなりましたが、初期の着ぐるみはちょうど人間が入って歩くのにちょうどいい体形でした。
そして、恐竜の進化の子孫である現代の鳥類はほとんどが二足歩行です。
また、二足歩行で地面だけでなく、水面上も高速で走るトカゲも南米には存在します。
類人猿や猿人、原人などが登場するまえから、生物たちは二足歩行で地球上を闊歩していたのです。
そして、それからかなり遅れて登場した人類とチンパンジーの共通の祖先である古い類人猿「ダヌビウス」も、デシルヴァさんによれば樹上で直立二足歩行していたらしいのです。
しかも、その化石から推定するに、そのまま地上に降りても同じように二足歩行ができたと考えられています。
それではなぜ、現代のチンパンジーやゴリラは、ときどき二足歩行することはあっても、移動の中心的な手段が両手をつく「ナックルウオーク」になっているのでしょうか。
デシルヴァは、ここで「進化の行進図」の方向を逆に考えます。
「ダヌビウス」は新しい環境に適応した移動手段として二足歩行になり、そこからさまざまな類人猿や猿人が生まれました。
だから直立二足歩行ができた類人猿や猿人、原人等の種類は数多くいたのです。
実際に化石人類として発見されている人類の祖先は25種にも及ぶそうです。
つまり、人類の祖先は大昔、1000万年以上も様々な種類で二足歩行をし続けていたのです。
そこから「直立」するようになった種も複数あり、現生人類はその一種ということになります。
ハウエルの人類進化の行進図(1965)。猿から人へ一直線に進化したようなイメージを与えるが、これはある目的をもって作られたもの、意図的に間違えているという認識が必要である。人の成長史と文明の発展史は同じようで向きが違う。Renaissance=ギリシャ時代の方が遥かに優れていたことを示している
— プリン好き?? (@dynamitesikoku) November 3, 2019
チンパンジーのほうが進化したのかもしれない
一方、二足歩行の共通祖先から別の進化の系統に進んだチンパンジーは、むしろ、ナックルウオークを移動手段としてあらためて選択した種だったということになります。
そのカギを握るのは手の骨格。
本書によれば、600万年前の化石類人猿の手の骨格は、親指と他の指が向かい合わせになる点など、今の人類のそれとほとんど変わっていないのですが、チンパンジーの手の骨格は、それに比べ指が長く、木から落ちないように進化しているのです。
以前はチンパンジーの手の骨格から人類の手の骨格に進化した理由が検討されてきましたが、実際には逆の可能性が高いわけです。
そうなれば、チンパンジーのほうが、様々な理由で二足歩行からナックルウオークに「進化」したのであって、その逆ではないということになります。
一応、デシルヴァは、「定説」であるナックルウオークから二足歩行に進化したという仮説も残しておく必要はあるというのですが、いまのところ、これを証明する化石は発見されていないということです。
だから、赤ちゃんがハイハイしてから歩き出す、という順番に人類の進化上の意味はないとも言い切れるのです。
さて、なんどか言及してきた「人類進化の行進図」ですが、本書には、ちょっと変わった「行進図」が掲載されています。
それは、木にぶら下がった類人猿が地上に降り立ったときからほぼ直立二足歩行で歩いた姿が描かれ、その後は、メスの人類の祖先が、胸に食料やこどもを抱え、妊娠して歩く姿が描かれているのです。
妹の歩き方が変だったから「人類進化の行進図の途中みたいになってるよ」って言ったら、慌てて背筋伸ばしてスッスッと歩きながら「完成した?!完成した?!」って言い出して、よく分からないけど可愛い pic.twitter.com/rfg64fmcHm
— ジューシーフルーツ井上 (@magro343) April 2, 2015
偏見に支配された「オス」中心の人類進化の仮説
本書の最後で古生物学者の更科功さんが「解説」で述べている通り、人類の進化についての仮説には、無意識の差別的偏見が潜んでいます。
それはオスがメスに餌を運び、オスどうしで闘争するのに武器を手にする必要があったことで、二足歩行に進化し、犬歯も小さくなったというもの。
オス中心の進化説です。
しかし、現代の狩猟採集民族を見ればわかる通り、植物食が中心の初期の人類は、メスが食料採集で中心的な役割を果たしていた可能性は高く、生物としての繁栄の条件である子どもに多くの食料を運ぶためにも、直立二足歩行と手の自由がある方が有利だったと考える方が自然です。
本書では、直立二足歩行が人類の脳や共感の感覚などに与えた影響について興味深い考察もあり、人類が地球上で他の生物たちを押しのけて繁栄してきた理由がわかるような気がしてくるのです。
しかし、その結果としての気候変動や戦争が収まらない現代に生きていると、「ヒトはサルから進化してきた」という考え自体をやめ、ヒトもサルも共通の祖先からの進化のあり方が違っていた子孫同士、と考えるほうが、今後の地球を考えるにはふさわしいのではないか。
そう考えさせられる一冊となっています。
「生命はたくさんの枝を分岐させ、絶滅という死神によって絶えず剪定されている樹木なのであって、予測された進歩の梯子ではない」(人類進化の行進図の否定)
— カミヤナオキ (@gotttal) January 2, 2013
直立二足歩行の人類史 人間を生き残らせた出来の悪い足 ジェレミー・デシルヴァ (著), 赤根洋子 (翻訳) 文藝春秋 (2022/8/10) 2,860円
「定説となっている考えを、論理的に打ち砕く破壊力を持っている」
――更科功氏、驚愕!
生命40億年の歴史のなかで、人類だけが直立二足歩行をして生き延びた。
それはいったいなぜなのか?
直立二足歩行の起源とは?
現役バリバリの古人類学者にして、「足と足首の専門家」である著者が、レジェンド人類化石や最新化石、さらには現代人の歩行や二足歩行ロボットの研究現場までを訪ね歩き、この永遠の疑問に迫る、痛快科学ノンフィクション。
チンパンジーと人類が分岐したのは約600万年前と言われる。四本足で歩いていた共通祖先から人類は二本足で立ちあがり、やがて道具を手にした……そうした一本道のイメージで人類進化をとらえている人は多いだろう。
しかし、著者が訪ねたドイツの発掘現場には、衝撃的な化石が待っていた。
人類揺籃の地であるアフリカではなくヨーロッパの、1100万年も前の地層で、「樹上で」二足歩行していた類人猿「ダヌビウス・グッゲンモシ」の化石が見つかったのだ。
さらに近年、同じく樹上で二足歩行していた「ルダピテクス・フンガリクス」も発見された。
一方、定説で想定されている「600万年前頃の、四足歩行する大型類人猿」という、人類とチンパンジーの共通祖先の化石は、いまだに見つかっていない。
……もしかして、1000万年前頃のヨーロッパには、樹上で二足歩行する類人猿がいろいろいたのかもしれない。
そのなかの一つの系統が、アフリカに進出して、立ったまま地上生活を始めたのかもしれない。
さらに、著者は新種の古人類「アウストラロピテクス・セディバ」が、現代人とは異なる歩き方をしていたことを突き止める。
これまで積み上げられてきた人類史は、いま大きく動こうとしているのか。
人類が立ちあがったのではなく、チンパンジーが手をついた? さまざまな歩き方の人類があちこちでさかんに歩き回っていた?
人間が人間になれたことに、二足歩行はどう役立ったのか?
現在もっとも熱い分野の最先端の現場を生き生きと楽しく活写する、古人類学愛に満ちた一冊。読めばきっと、すばらしく便利でものすごく不便なこの二本の足が愛おしくなる。
「新たな人骨化石の出現や解析方法の深化で今までに教わった歴史とは違う事実だろうことを知ったのは有意義でした。
少し後半部分が冗長ですが、全体としては面白い本だと思います。」「個人的には歩くことの意義を説く第三部以降がとくに関心をもって読むことができた。今後も無理のない範囲で歩くことを継続していこうと思わせてくれるのに十分な内容であり、終章で提示された善悪あわせもつ人間に対するポジティブな捉え方も収穫だった。」
「著者のジェレミー・デシルヴァは、最新の研究の流れまでを臨場感豊かに描き出しています。人類史に関心のある者には見逃せない一冊です。」
|
|











