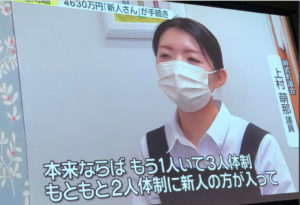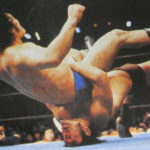「それって食わず嫌いでしょ?」クルマ好きなオジサンがなぜか使いたがらない先進機能
一度試せば手放せなくなるのが最新モデルの「先進運転支援機能」も、クルマ好きなベテラン勢は「自分で運転操作したほうがラク」と考える人も多い様子。
しかし実のところ、まだ使ったことがないだけなのかもしれません。
目次
一度試せば実感できるはず!? 最新モデルの先進運転支援機能
カメラやセンサー技術などの発展により、クルマの運転を支援する先進機能の普及が急速に進んでいます。
ロングドライブで渋滞にハマってしまったときなどに使えば、疲労の軽減につながります。
ところがクルマ好きのオジサン勢に訊くと、案外こうした機能を活用できていないといいます。
なぜでしょうか。
そもそもクルマ好きと呼ばれる人たちは「運転行為が苦ではない」という大前提があります。
長時間に渡りアクセルやブレーキ、ステアリングの操作をおこなうこと自体が、ドライブの行為のひとつとして楽しめるので、わざわざ先進機能で「支援」してもらう必要もない、と感じている訳です。
SNSでも「(運転支援機能は)大きなお世話だ」「自分で操作したほうがラク」といった意見が、クルマ好きなベテラン勢を中心に発信されていることもしばしば見られます。
しかしせっかく装備されている便利な機能だけに、ベテランドライバーやクルマ好き勢だって有効活用しない手はありません。
ここで改めて「使いこなしたい便利な先進運転機能」をご紹介します。
「アダプティブクルーズコントロール(ACC)」
「アダプティブクルーズコントロール(ACC)」は、設定した車速を維持したままアクセル操作を解放してくれる「クルーズコントロール」に「Adaptive(アダプティブ:適応性のある)」な機能を追加したものです。
具体的には、先行車両がいる場合は適切な車間距離をもって追従し、渋滞時に先行車両が停止した場合には、自車も自動的に停止させます(メーカーや車種により適用条件は異なります)。
レーダーやカメラなどのセンサー技術を用いて先行車両を認識し、アクセルやブレーキ操作を代行してくれます。
さらに車種によってはACCと連動し、車線を維持するためのステアリング操作の補助もしてくれる、いわば「半自動運転」というべき一歩進んだ機能を備えるクルマも増えています。
普及初期のころは、車種によってはやや不自然な動作のため「自分で運転操作したほうがいい」と感じるケースもありましたが、近年はかなり自然に稼働してくれます。
一度慣れてしまえば、次からはもう手放せなくなる…そんな先進運転支援機能の代表格といってよいでしょう。
納車して初めて【ACC】アダプティブクルーズコントロールというやつを使ってみたんですがめっちゃ快適というか,すげぇってなりました
— ちーの (@Chi8non) May 18, 2022
「オートライト」
2020年4月から新型車への装備義務化がはじまった「オートライト」機能は、まさに読んで字のごとく、周囲の明るさに応じてヘッドライトを自動で点灯してくれる便利機能です。
夕暮れの時間帯は、ドライバーからは周囲が見えていても、歩道側や対向車線などからはクルマが見えづらいことがあり、早期のヘッドライト点灯が求められます。
オートライト機能は、そんなときに素早く反応してくれます。
ただし車種や年式により、いくつかの機能差があります。
すでに10年数以上前から広く普及しているのは、ライトスイッチで「AUTO/ON/スモール/OFF」を選択するタイプ。
ただ自らON/OFFするのが当たり前になっているドライバーのなかには、そもそもAUTOの存在を知らない人すらいるといいます。
一方最新モデルでは、AUTOがデフォルト設定となっているものも多く、任意でライトを消す際にはライトスイッチを長まわししないとOFFできないようになっています。
エンジン再始動後は再びAUTO状態に戻ります。
ベテランドライバーに訊くと「橋脚下を連続して通過するような場合、頻繁にライト点滅を繰り返すのが、先行車をパッシングしているようで嫌だ」と話します。
とはいえオートライトが点灯するのは、周囲が暗いということの証しです。
うっかり無灯火で走るほうがよほど危険ですから、AUTOに入れっぱなしにしておいたほうが結果的に安全だといえるでしょう。
??「高速のトンネル入ってもオートライトつかへんねんけど」
??「スイッチちゃんとなってますね」
??「なんでやろなぁ…」
??「まさか思いますけどサングラスしたままトンネル入りました???」
??「………」— 洋梨 (@MechaYou_nashi) May 17, 2022
「オートブレーキホールド」
シフトをD(ドライブ)に入れて走行時、信号待ちや渋滞などで一時停車した際、長くブレーキを踏み続けるのは地味に疲れるものです。
そんなとき、一度ブレーキを踏み込んでしまえば、足を離しても停止状態を維持してくれるのが「オートブレーキホールド」機構です。
再発進時も、アクセルをスッと軽く踏み込めば自動で解除してくれるので、ボタン操作などは必要ありません。
電子式パーキングブレーキの機能を用いた便利装備として、軽自動車に至るまで近年急速に採用が拡がっています。
前出のACCを装備するクルマなら、オートブレーキホールド機能もセットで備わっているケースが多いです。
ACC同様に、いちど使ってみると次からはないクルマが考えられなくなるほど、非常に便利な機能といえます。
納車されて7ヶ月。渋滞なにそれ美味しいの?という地域に住んでる上、渋滞とは無縁の所に行く事が殆どで使う機会がなく…本日初めてオートブレーキホールドを使う。
こりゃ便利。標準仕様である機能なので、使ってナンボですね(‘ω’) pic.twitter.com/eQidqKv3S0— カンチャン (@TRNR_kan) May 21, 2022
あくまでも補助的な機能という認識を
紹介した先進装備は、いずれも運転を「支援」する「補助的な機能」だということは、忘れてはいけない「原理原則」です。
どんな先進運転機能を利用するにせよ、「発進」「加速」「ハンドル操作」「停止」といった運転の主体者は、常にドライバーにあります。
もし操作から解放されていたとしても、いつでも自らブレーキやアクセル、ステアリング操作が対応できるよう「構え」の姿勢をとっていることが肝要となります。
例えばACC利用時にひざを立ててペダルから右足を遠ざけたり、よそ見をしたりするのは論外です。
緊急回避が必要なとき、瞬時に対応できるよう心がけましょう。
ネットの声
「安全・快適を求めた結果の機能。メーカーの技術の結晶かと思います。でも、最終的に操作をするのは人間な訳ですから運転が楽になる程、人が車を運転する技術は衰えていくのも事実ですね。MTからATに進化した結果「踏み間違い」が起こっているのが良い例。技術の向上と人間の能力のバランスが進化の上で大事なんだろうなぁと思いました。」
「ついこの間、有吉クイズで出川哲朗さんがドライブをしている回を思い出した。出川さんは機械を信用していなくて、カーナビやETCを全く使っていないとのことだった。楽しそうなのは何よりだし、拘りがあるのは悪くないが、その反面、同乗者がいる場合は面倒くさいことも多いだろう。例えば、恋人を乗せてどこかに行くとなったら、同乗者からすると早く目的地にたどり着きたいのに道に迷ったり現金のやり取りで無駄に待たされる。検証を重ねた上で市場に出回る機械もミスをすることはあるかもしれないが、人間の勘もそこまで信用出来るものでは無い。
先進的な機能を使うか使わないかは自由だが、あまり先入観は持たないでほしいのが正直なところ。」「オートパイロットが普及しても基本的にパイロットの技量が下がったということはなく、事故は激減してきたという事実があります。
先進機能のサポートがあれば、自分は周囲のモニタリングなど、より危険を回避することに集中できると考えています。
新しいことに慣れる、学ぶことを放棄して、今までのやり方に固執する人が本当に多くなったと思います。
結局、社会が高齢化して柔軟ではなくなっているのでしょう。」