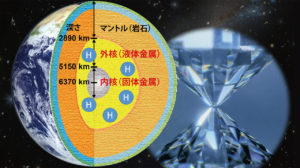本当の“生活苦”はこれから…ニッポンの高齢者を苦しめる「おカネの三重苦」
どうやら、この国の為政者たちは国民生活が苦しくなることに“痛みを感じない”らしい。
すでに原油価格の上昇などにより、物価の上昇が続いていますが、実質的な給与所得の減額につながる社会保障費などの引き上げは、これからが本番です。
目次
ガソリン、食料品、高速道路など続々と値上げ
残念なことに、ガソリン・灯油価格はもとより、昨年末からは多くの食料品が値上げされ、さらには、電気・ガス料金も値上げされ、22年4月からは“便乗値上げ”としか思えない首都高速道路の通行料金までもが値上げされます。
こうした食料品や電気・ガス料金などの値上げについては、多少の自己防衛策もありますが、社会保障費関連の引き上げは避けようがありません。
3つの負担増
10月の衆議院選挙で岸田文雄総理が「公的価格の見直しによる介護士、看護師、保育士などの収入増加」を掲げています。
これには、収入増加の財源を公定価格とすれば、国民に大きな負担を強いることになるとことが指摘されています。
医療における公定価格とは「診療報酬」を指します。
この診療報酬の財源は、患者負担と健康保険料、国や地方自治体による公費で賄われているのです。
案の定、政府は22年度の診療報酬を引き上げる方向で検討を進めており、改定率はプラス0.43%になると見られています。
この引き上げにより、給与所得などから徴収される健康保険料が増額することになります。
同様に、介護における公定価格とは「介護報酬」を指します。
財源は40歳以上の国民が生涯にわたって支払う介護保険料と公費で賄われているのです。
介護保険料はすでに、21年4月から引き上げられており、全国平均の保険料は月額5869円から同6014円に増額しました。
この介護保険料は24年にも引き上げられる予定で、厚生労働省の試算によると、同6856円となります。
高齢化の進展とともに、介護保険料率は引き上げが続いており、40歳以上にとっては年々負担が増しています。
健康保険料、介護保険料と同様に引き上げが行われる予定なのが雇用保険料。
雇用保険の積立金が枯渇し、いずれ雇用保険料の引き上げが行われることが指摘されています。
政府は2月1日の閣議で、雇用保険法などの改正案を閣議決定しました。
これにより、労使が折半で負担する雇用保険料は、賃金の0.9%から4~9月は0.95%に、10月以降は1.35%に引き上げる方針です。
月給30万円のサラリーマンの場合、月900円の保険料が月1500円に増額することになります。
このように、物価の上昇に加え、健康保険料、介護保険料、雇用保険料といった社会保障費の増額が待ち構えているのです。
そして、より大きな痛手を受けそうなのが高齢者です。
介護保険料は死ぬまで支払うので、保険料の引き上げは、当然、高齢者も例外ではありません。
加えて、22年10月から後期高齢者(75歳以上)で、一定以上の所得がある高齢者の医療費の自己負担割合が1割から2割に引き上げられます。
すでに、年収383万円以上の現役並み所得がある後期高齢者は3割負担となっており、これを年収が200万円以上の後期高齢者についても2割負担とするのです。
高齢者の多くは、食費以外の公共料金・健康保険料・健康保険料住民税等がガッチリ引き去られ、外食そのものができないのです。私も2年以上外食やテイクアウトなしの生活をしています。「高級焼肉店で平気で30万~40万使って」となると、涙も枯れます。助成は庶民へ。 https://t.co/Q8FbVPk2zS
— spononvictory (@spononvictory) February 6, 2022
年金支給額まで減額
その上、22年度の年金支給額が前年比で0.4%減額されるのだから“たまったものではありません”。
年金支給額は、物価スライドとマクロ経済スライドという方法によって決められるのですが、22年度の支給額は物価スライドにより、21年の名目賃金が前年比0.4%減少したことで、勤労者の所得減少に連動させて減額することになりました。
ちなみに、マクロ経済スライドは平均余命の伸び率と年金受給者の増減率をベースとして、年金受給者の増加に合わせて、年金支払額を減らす方法ですが、物価スライドで年金受給額が減額される時には適用を“先送り”するため、本来は0.3%削減する予定だったが見送られました。
ただし、“先送り”のため、来年度には実施される予定で、23年度はマクロ経済スライドで年金受給額は先送り分の0.3%と合わせて0.5%程度の減額になるのではないかと見られています。
このように、高齢者は年金所得が恒常的に減少していく一方で、社会保障費の負担が増大しているのです。
2000 年の段階で、高齢者 1 人の年金受給分を 現役で働いている 3.6 人で支えていた。 このままでいくと
2025 年には 1.8 人で 1 人を支え、
2050 年には 1.2 人で 1 人を支えること つまり月収 25 万円の人は
20 万円を年金に払い
5 万円で生活しなければならないことになる— タカシ (@feryuni12) February 6, 2022
負のスパイラル
現在、生活保護受給世帯の半数以上(21年10月時点で55.5%)は、65歳以上の高齢者世帯となっています。
高齢者の健康保険も年金も、現役世代からの徴収によって支えられています。
従って、高齢者の社会保障費負担を増やし、年金受給額を減額し、現役世代の負担を軽減しようという考えはわからなくもありません。
しかし、高齢者が物価上昇や社会保障費の増加を受ければ、生活苦による生活保護受給世帯数の増加に拍車をかけることなり、それは社会保障費の増加という“負のスパイラル”につながるのです。
岸田政権は経済界に3%以上の賃上げを要請するなど、賃金引上げに非常に前向きです。
しかしながら、賃金が上がっても、健康保険料や雇用保険料、介護保険料といった社会保障費が引き上げられることで、賃金上昇効果が相殺されてしまうことには“無頓着”のようです。
社会保障費を負担しても十分な形で実質賃金が上がり、これをベースに年金受給額が増加するという“正のスパイラル”になるように、経済成長を促す政策を進め、社会保障制度の抜本的な見直しを行う必要があります。
〇老人福祉法
高齢者の心身の健康、生活の安定を保障するために制定された。んで老人居宅生活支援事業、老人福祉施設などが定められてる。原則としては介護保険が優先されるけど何らかの事情で介護保険を利用できませんって時に老人福祉法の福祉の措置ってやつで市町村からサービス提供してもらえる。— 水中のワニ看護学生 (@mizuwani_111) February 6, 2022
ネットの声
「自公政権は庶民の生活苦など微塵も感じていないであろう。スーパーの安売りが高齢者が集まって混雑している。決して十分な年金も貰えていないのに、介護保険料、医療負担の増加、そして追い打ちをかけるように年金の減額。コロナ禍での給付支援もおおざっぱで本当に困っている人には支援が行き届かぬ現状。自分たちはのうのうと税金で高級ホテルでの会食を繰り返している。早々に政権交代を図らねばこの国はひどいことになる。」
「「貧すれば鈍する」これは研究でも証明されていて経済的不安が常にある状態だと思考能力が落ちるらしい。
国民の思考能力が低くなると与党は選挙で有利になったり、やりたい放題しても国民に文句を言われないなどメリットが大きくなる。
最近ひょっとしたら自民党は故意に時間をかけて国民をこの状態に持っていってるのではないかと思うようになった。」「本人は構ってもらいたいからか孫にプレゼントやお金を送る けど傍らから見たらこれこそ無駄だと思うよ
以前テレビで生活保護の高齢者がお金が足りないと訴えていたがその中に孫へのプレゼントが毎月5,000円ってどうなの?と思った」「年金が安くて生活できないって今の高齢者が文句を言ったとしても、実態からいうともらい過ぎであることの方が多いんですよね。若い人たちが高齢者になったときには絶対にそんな額もらえないですから…。」